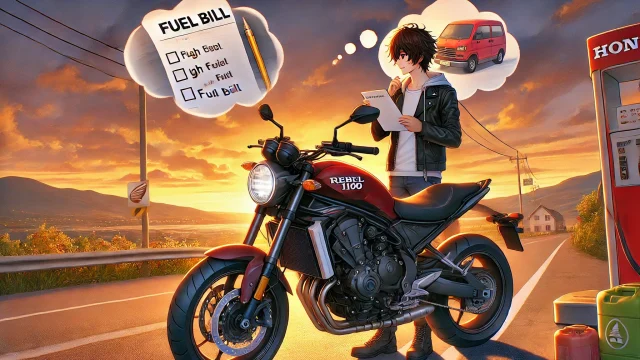ホンダが誇るV型4気筒エンジンを搭載した孤高のスポーツツアラー、VFR800F。その洗練されたデザインと独自のエンジンフィールは、多くのバイクファンを魅了してきました。しかし、インターネット上では「VFR800F 不人気」「VFR800F 乗りにくい」といったキーワードを目にすることがあります。一体なぜ、このようなネガティブな評価が存在するのでしょうか?本当にVFR800Fは人気がなく、扱いにくいバイクなのでしょうか?
この記事では、そうした疑問に真正面から向き合い、VFR800Fが「不人気」や「乗りにくい」と言われる理由を探りつつ、その一方で多くのライダーから愛され続ける魅力や、実際の走行性能、乗り心地について、ユーザーレビューや様々な情報を基に徹底的に検証していきます。
VFR800Fの代名詞とも言えるHYPER VTECエンジン、その独特なフィーリングは評価が分かれるポイントかもしれません。また、スポーツツアラーとしての絶妙なライディングポジションや、決して軽くはない車重が「乗りにくい」と感じさせる要因なのでしょうか?生産終了となった今、中古市場での動向や価格も含め、VFR800Fの真の姿を明らかにしていきます。VFR800Fの購入を検討している方、かつて憧れた方、そして現役オーナーの方も、この記事を通じてVFR800Fの多面的な魅力を再発見していただければ幸いです。
- VFR800Fが「不人気」と言われる背景と、実際の人気や評価を分析
- 「乗りにくい」とされる要因(車重、ポジション、VTEC)を検証し、実際の乗り味を解説
- VFR800Fならではの魅力(V4エンジン、デザイン、ツアラー性能)を深掘り
- 中古車選びのポイントや生産終了による影響についても考察
VFR800Fは本当に不人気なのか?その理由と魅力
- VFR800F 不人気の噂 その根拠はどこにある?
- 独自のV4エンジンとHYPER VTEC 人気の源泉か、それとも?
- ライバル車種との比較 VFR800Fの立ち位置
- デザイン評価 時代を超えた魅力と好みの分かれる点
- 生産終了の影響 中古市場での人気と価格動向
- 熱狂的なファンを持つVFRシリーズ その歴史と人気の変遷
- 所有者の満足度レビュー 不人気説を覆す声
VFR800F 不人気の噂 その根拠はどこにある?
- 「不人気」というより「ニッチな人気」と表現するのが実態に近い。
- V4エンジンやVTECなど、独特の機構が万人受けしなかった可能性。
- 価格設定が比較的高めだったことも、販売台数に影響したか。
ホンダ VFR800Fに対して、一部で「不人気」というレッテルが貼られることがあるのは事実です。しかし、その根拠を探ってみると、単純に「人気がない」と断言するのは早計であるように思われます。まず考えられるのは、VFR800Fが決して「大衆向けのベストセラーモデル」ではなかったという点です。VFRシリーズは、ホンダの技術力を象徴するV型4気筒エンジンを搭載し、スポーツ性とツーリング性能を高次元でバランスさせた独自のポジションを築いてきました。特にVFR800F(RC79型)は、洗練されたデザインと上質な作り込みが魅力でしたが、その分、新車価格も比較的高めに設定されていました。同クラスの他のスポーツツアラーや、より尖った性能を持つスーパースポーツ、あるいは快適性を重視したアドベンチャーモデルなど、競合する車種が多様化する中で、VFR800Fの立ち位置はやや玄人向け、あるいは特定の価値観を持つライダー向けであったと言えるかもしれません。そのため、爆発的な販売台数を記録するには至らず、結果として「不人気」という印象を持たれる一因になった可能性があります。また、搭載されているHYPER VTEC機構も、その独特なフィーリングから好みが分かれる部分であり、一部のライダーからは敬遠された側面もあるかもしれません。回転数によって作動バルブ数が切り替わるVTECは、刺激的な加速フィールをもたらす一方で、切り替わり時の挙動変化を「扱いにくい」と感じる声も存在しました。しかし、これは裏を返せば、VFR800Fが没個性的なバイクではなく、明確なキャラクターを持っていた証拠とも言えます。熱狂的なファン、いわゆる「VFR乗り」と呼ばれる層が存在することからも、その魅力が一部のライダーには深く刺さっていたことがうかがえます。
さらに、「不人気」という言葉が使われる背景には、生産終了という事実も影響しているかもしれません。排ガス規制など様々な要因により、VFR800Fは2022年に惜しまれつつ生産終了となりました。人気モデルであれば生産が継続されるはず、という短絡的な思考から「不人気だったから生産終了したのでは?」と結びつけられるケースもあるようです。しかし、実際には規制対応の難しさや、市場全体のトレンドの変化など、複合的な理由が考えられます。実際にオーナーレビューやブログなどを調べてみると、VFR800Fに対する満足度は非常に高く、「買ってよかった」「最高のツアラーだ」といったポジティブな評価が数多く見られます。むしろ、「不人気」というよりは、「分かる人には分かる、ニッチで根強い人気を持つモデル」と表現する方が実態に近いのではないでしょうか。特定のキーワードだけを見て「不人気バイク」と判断するのではなく、その背景にある事情や、実際に所有しているユーザーの声を多角的に見ることが重要です。VFR800Fは、決して万人受けするタイプではなかったかもしれませんが、ホンダのこだわりが詰まった、唯一無二の魅力を持つバイクであることは間違いありません。
独自のV4エンジンとHYPER VTEC 人気の源泉か、それとも?
- V型4気筒エンジンはスムーズな回転フィールと独特のサウンドが魅力。
- HYPER VTECは低回転域の扱いやすさと高回転域のパワー感を両立させる機構。
- VTECの作動フィールは好みが分かれ、「不人気」や「乗りにくい」の一因とも言われる。
VFR800Fの心臓部であり、そのキャラクターを最も特徴づけているのが、水冷4ストロークDOHC4バルブV型4気筒エンジンと、そこに組み合わされたHYPER VTEC機構です。この組み合わせこそが、VFR800Fの人気の源泉であると同時に、一部で「不人気」や「乗りにくい」と言われる要因にもなっています。まず、V型4気筒エンジンそのものの魅力について見ていきましょう。V4エンジンは、直列4気筒ともV型2気筒とも異なる独特の回転フィールと排気サウンドを持っています。一般的に、低回転域からトルクフルで、かつ高回転までスムーズに吹け上がる特性を持ち、振動も少ないとされています。VFR800FのV4エンジンもその例に漏れず、シルキーとも評される滑らかな回転上昇と、官能的とも言える独特のエンジンサウンドは、多くのライダーを魅了してきました。特に、ホンダのV4エンジンはレースシーンでの活躍(RCシリーズなど)のイメージも強く、その技術的な先進性や高性能なイメージも、VFRシリーズの人気を支える要素の一つでした。一方で、HYPER VTEC機構は、より複雑な評価を受けています。この機構は、一定のエンジン回転数(RC79型では約6,500rpm)を境に、1気筒あたりに作動するバルブの数を2バルブから4バルブに切り替えるものです。低回転域では2バルブ作動とすることで、燃費性能や低速トルクの扱いやすさを向上させ、高回転域では4バルブ作動とすることで、吸排気効率を高め、パワフルな加速感を得ることを狙っています。このアイデア自体は非常に画期的であり、二つの異なるエンジン特性を一台で味わえるというメリットがあります。
しかし、このバルブ数が切り替わる瞬間のフィーリングが、ライダーによって評価の分かれるところです。VTECが作動すると、エンジン音の変化とともに、明確なパワー感の盛り上がり、いわゆる「VTECゾーン」に入った感覚を味わえます。これを「刺激的で楽しい」「VFRならではの醍醐味」と感じるライダーがいる一方で、「切り替わり時のトルク変動やサウンドの変化が唐突で違和感がある」「スムーズさに欠ける」「コーナーリング中に作動すると挙動が不安定になる」といったネガティブな意見も存在します。特に、初期のVTECシステム(VFR800/RC46後期)では、この切り替わりがより顕著だったため、「ドンツキ感がある」と評されることもありました。VFR800F(RC79型)では、このVTECの作動フィールはかなり洗練され、スムーズになったとされていますが、それでも独特のフィーリングが残っており、これを好むか好まないかが、VFR800Fの評価を大きく左右する要因の一つとなっています。VTECを搭載しないシンプルなエンジンフィールを好むライダーにとっては、この機構が「余計なもの」「乗りにくさの原因」と映る可能性があり、それが「不人気」という評価に繋がっている側面も否定できません。しかし、逆にこのVTECのフィーリングこそがVFRの魅力だと考える熱心なファンも多く存在します。結局のところ、V4エンジンとHYPER VTECは、VFR800Fの個性を際立たせる最大の特徴であり、その評価はライダーの好みや価値観によって大きく異なる、非常にパーソナルな部分であると言えるでしょう。
ライバル車種との比較 VFR800Fの立ち位置
- 競合はNinja 1000SX、GSX-S1000GTなどリッタークラスのスポーツツアラー。
- VFR800FはV4エンジンとVTECによる独自の走行フィールで差別化。
- 他モデルに比べ、やや玄人好みでニッチなポジションにあった。
VFR800Fが市場でどのような立ち位置にあったのかを理解するために、ライバルとなる車種と比較してみましょう。VFR800Fは800ccクラスのスポーツツアラーというカテゴリーに属しますが、近年このクラスは選択肢が限られており、実質的なライバルは1000ccクラスのモデルとなることが多かったです。代表的なライバルとしては、カワサキのNinja 1000SXや、スズキのGSX-S1000GTなどが挙げられます。これらのモデルは、いずれも直列4気筒エンジンを搭載し、パワフルな走行性能と快適なツーリング性能を両立させて人気を集めています。これらのライバルと比較したとき、VFR800Fの最大の特徴であり、差別化ポイントとなるのが、やはりV型4気筒エンジンとHYPER VTEC機構です。Ninja 1000SXやGSX-S1000GTが、比較的オーソドックスで扱いやすいパワーデリバリーを持つ直列4気筒エンジンを採用しているのに対し、VFR800FはV4ならではの鼓動感とスムーズさ、そしてVTECによる二面性のあるキャラクターを提供します。最高出力やトルクといったスペック面では、リッタークラスのライバルにやや劣る部分もありますが、VFR800Fはその独特のエンジンフィールで勝負していたと言えます。また、デザイン面でも、VFR800Fはホンダらしい洗練された、やや大人びたスタイリングを持つのに対し、ライバル車はよりアグレッシブで現代的なデザインを採用している傾向があります。これも好みが分かれるポイントでしょう。装備面では、VFR800F(RC79型)はトラクションコントロールやETC車載器、グリップヒーターなどを標準装備し、ツアラーとしての快適性を高めていましたが、ライバル車も近年は電子制御サスペンションやクルーズコントロール、クイックシフターなど、より先進的な装備を充実させてきており、装備競争の面ではやや厳しい状況にあったかもしれません。
価格設定も比較のポイントです。VFR800Fの新車価格は、ライバルとなるリッタークラスのスポーツツアラーと同等か、やや高めの水準でした。800ccという排気量を考えると、コストパフォーマンスの面で不利と捉えるユーザーもいたかもしれません。これらの比較から見えてくるのは、VFR800Fがライバルひしめく市場において、独自のエンジン形式や機構、そしてホンダならではの上質な作り込みといった、明確な個性とこだわりを持ったモデルであったということです。それは、爆発的な人気を得るための最大公約数的なアプローチではなく、特定の価値観を持つライダーに深く響くような、ある意味でニッチなポジションを狙った戦略だったのかもしれません。結果として、販売台数ではライバルに及ばなかったかもしれませんが、「VFRでなければダメだ」という熱心なファンを生み出すことに成功したモデルとも言えます。「不人気」という評価は、こうした市場での立ち位置や販売戦略の結果を反映している部分もあると考えられます。しかし、それは決してバイクとしての魅力がないことを意味するのではなく、むしろ独自の価値を持っていたことの裏返しでもあるのです。
デザイン評価 時代を超えた魅力と好みの分かれる点
- VFR800F(RC79)のデザインは洗練されており、上質感を求める層に評価された。
- フロントのX型LEDヘッドライトが特徴的だが、このデザインは好みが分かれる。
- 全体的に大人びた、落ち着いたスタイリングを持つ。
バイクを選ぶ上で、デザインは性能と同じくらい、あるいはそれ以上に重要な要素です。ホンダ VFR800F(特にRC79型)のデザインは、その評価が分かれるポイントの一つであり、「不人気」と言われる一因になった可能性も、逆に根強いファンを生んだ理由にもなり得ます。VFR800F(RC79型)のデザインは、先代モデル(RC46後期)のやや丸みを帯びた形状から一新され、エッジの効いたシャープなラインで構成されています。全体的に非常に洗練されており、ホンダらしいクリーンで上質な雰囲気を醸し出しています。特に、カウルの合わせ面の精度や塗装の質感など、細部の作り込みは非常に丁寧で、所有感を満たしてくれるレベルにあります。この大人びた、落ち着いた雰囲気のデザインは、派手さやアグレッシブさを求めるライダーには物足りなく映るかもしれませんが、上質で飽きのこないデザインを好む層からは高く評価されました。「長く付き合えるデザイン」「派手すぎず、地味すぎず、ちょうど良い」といった声が多く聞かれます。スポーツツアラーとして、長距離を走っても疲れにくいカウリング形状と、ライダーを包み込むような一体感のあるフォルムは、機能美としても優れています。特に、センターアップマフラーからサイドマフラーに変更されたことで、パニアケースの装着が容易になり、左右のデザインバランスも向上した点は、ツアラーとしての機能性とデザイン性を両立させる上で評価できるポイントです。
一方で、VFR800Fのデザインで最も特徴的であり、賛否両論を巻き起こしたのが、フロントマスク中央に配置された「X」字型のLEDポジションランプ付きヘッドライトです。これは当時のホンダの他のモデルにも採用されていたデザインモチーフですが、VFR800Fにおいては特に印象的で、その先進性をアピールする要素でした。しかし、このX型デザインに対しては、「個性的でかっこいい」「VFRらしくて好き」という肯定的な意見がある一方で、「奇抜すぎる」「昆虫みたいで好みではない」「もう少しオーソドックスな方が良かった」といった否定的な意見も少なくありませんでした。バイクの「顔」とも言えるフロントマスクのデザインは、全体の印象を大きく左右するため、この部分の好みがVFR800F全体の評価に繋がった可能性はあります。カラーリングに関しても、VFR伝統のレッドや、落ち着いたホワイト、精悍なブラックなどが用意されましたが、比較的オーソドックスな選択肢が中心でした。もう少し遊び心のあるカラーリングを求める声もあったかもしれません。デザインの評価は、個人の主観に大きく左右されるため、一概に「良い」「悪い」と決めつけることはできません。VFR800Fのデザインは、決して万人受けするタイプではなかったかもしれませんが、ホンダのデザイン哲学と、VFRというモデルが持つべき品格や機能性を表現しようとした意欲的な試みであったと言えるでしょう。結果として、そのデザインに強く惹かれるファンがいる一方で、受け入れられない層もいた、というのが実情に近いのかもしれません。
生産終了の影響 中古市場での人気と価格動向
- 2022年に生産終了となり、新車での入手は不可能に。
- 中古市場では、V4エンジン搭載の希少性から一定の人気と需要を維持。
- 価格は年式や状態によるが、極端な値上がりや値下がりは少ない傾向。
ホンダ VFR800Fは、残念ながら2022年モデルを最後に生産終了となりました。これは主に、年々厳しくなる排出ガス規制(ユーロ5相当)への対応が困難になったことが理由とされています。生産終了という事実は、VFR800Fが「不人気」だったからではないか、という憶測を呼ぶ一因にもなりましたが、むしろこの生産終了によって、VFR800F、特にV型4気筒エンジンを搭載したスポーツツアラーの希少価値が高まり、中古市場での注目度が変化しています。現在、新車でVFR800Fを入手することはできません。そのため、VFR800Fに乗りたいと考えた場合、必然的に中古車を探すことになります。生産終了が発表された直後は、駆け込み需要や将来的な価値上昇を見込んだ動きから、一時的に中古車価格が上昇する傾向も見られましたが、その後は比較的落ち着いた値動きを見せているようです。極端なプレミアム価格が付くような状況にはなっていませんが、かといって不人気車のように大きく値崩れしているわけでもありません。これは、VFR800Fが持つ独自の魅力、特にV4エンジンに対する根強いファンや、程度の良いスポーツツアラーを探している層からの安定した需要があることを示唆しています。中古市場では、年式(特に最終モデルに近い高年式)、走行距離、車両の状態(傷、錆、カスタムの有無など)、そして装備(純正パニアケース付きなど)によって価格は大きく変動します。特に、最終型に近いRC79後期のモデルや、走行距離の少ない極上車は、比較的高値で取引される傾向にあります。一方で、初期のRC79や、走行距離が伸びている車両、あるいは転倒歴のある車両などは、手頃な価格で見つけることも可能です。生産終了となったことで、今後、状態の良いVFR800Fは徐々に減っていくことが予想されます。そのため、もし購入を検討しているのであれば、程度の良い個体を見つけたら早めに決断することも必要かもしれません。
また、生産終了モデルであるため、将来的な部品供給について不安を感じる方もいるかもしれません。ホンダは比較的長期間、部品供給を続けるメーカーとして知られていますが、それでも年数が経てば供給が終了する部品も出てきます。特に外装パーツなどは、転倒などで破損した場合に入手が困難になる可能性も考慮しておく必要があるでしょう。しかし、エンジンなどの主要部品に関しては、ホンダのV4エンジンは長い歴史を持ち、一定の互換性を持つ部品もあるため、当面は大きな心配はないと考えられます。中古市場での価格動向や部品供給のリスクなどを考慮しても、VFR800Fが持つ魅力は色褪せていません。むしろ、新車では手に入らない希少なV4スポーツツアラーとして、その価値は今後も維持される可能性が高いと言えるでしょう。「不人気」どころか、中古市場では「指名買い」されることも少なくない、隠れた人気モデルとしての地位を確立しつつあるのかもしれません。購入を検討する際は、信頼できる販売店で車両の状態をしっかりと確認し、納得のいく一台を見つけることが大切です。
熱狂的なファンを持つVFRシリーズ その歴史と人気の変遷
- VFRシリーズはホンダの技術を結集したV4スポーツの象徴的存在。
- レース由来の高性能とツーリング適性を両立し、独自の地位を築いてきた。
- モデルチェンジごとに賛否両論ありつつも、根強いファンに支えられてきた歴史を持つ。
VFR800Fに対する「不人気」という評価を考える上で、VFRというバイクシリーズが持つ長い歴史と、その中で培われてきた独特のファン層について触れないわけにはいきません。VFRシリーズのルーツは、1980年代のホンダのレース活動、特にNRやRVFといったワークスマシンに遡ります。その技術をフィードバックして生まれた市販モデルがVFシリーズであり、その進化形として1986年に登場したのが初代VFR750F(RC24)です。当時のVFR750Fは、レースで培われた高性能なV4エンジンを搭載しながらも、安定したハンドリングと快適なライディングポジションを両立させ、スーパースポーツとツアラーの要素を高次元で融合させた「スーパーツポーツ」という新たなジャンルを切り開きました。その完成度の高さから、国内外で高い評価を受け、VFRシリーズの輝かしい歴史の幕開けとなりました。その後もVFRシリーズは、常にホンダの最新技術が投入されるフラッグシップモデルの一つとして進化を続けます。プロアーム(片持ち式スイングアーム)を採用したVFR750F(RC36)、排気量を800ccに拡大し、PGM-FI(電子制御燃料噴射装置)を搭載したVFR800(RC46前期)、そして物議を醸しつつも革新的なHYPER VTECを採用したVFR800(RC46後期)へと、モデルチェンジを重ねるごとに、その時代におけるホンダの技術的な挑戦が反映されてきました。これらのモデルは、それぞれに熱狂的なファンを生み出し、「VFR乗り」と呼ばれる、シリーズに対する愛着の強いライダー層を形成してきました。彼らにとってVFRは、単なる移動手段ではなく、ホンダの技術力とこだわりが詰まった特別な存在であり、所有すること自体に喜びを感じるバイクなのです。
しかし、その一方で、モデルチェンジごとに加えられる新技術やデザインの変更に対しては、常に賛否両論がありました。例えば、VTECの採用は、パフォーマンスの向上をもたらした一方で、従来のVFRが持っていたスムーズで扱いやすいエンジンフィールを好む層からは、必ずしも歓迎されませんでした。デザインに関しても、時代ごとのトレンドを取り入れつつ進化してきましたが、特定のモデルのデザインを至高とするファンも多く存在します。VFR800F(RC79)も、こうしたVFRシリーズの歴史の流れの中に位置づけられます。先代からのフルモデルチェンジとして、デザインを一新し、エンジンや足回りを熟成させ、最新の電子制御技術を導入しました。しかし、それは同時に、一部のファンが抱いていた「VFRらしさ」のイメージとは異なる部分もあったかもしれません。例えば、かつてのレーサーレプリカ的な雰囲気は薄れ、より洗練されたスポーツツアラーとしての性格が強まりました。こうした変化が、「昔のVFRの方が良かった」という声を生み、「不人気」という評価に繋がった側面もあるでしょう。しかし、見方を変えれば、VFRシリーズは常に時代の要請や技術の進歩に合わせて変化し続けてきたモデルであり、その時々で最高のスポーツツアラーを目指してきた結果とも言えます。その歴史を通じて、常に一定数の熱心なファンに支えられ続けてきたことこそが、VFRシリーズの本当の人気を物語っているのではないでしょうか。
所有者の満足度レビュー 不人気説を覆す声
- 実際のオーナーレビューでは、VFR800Fに対する満足度は非常に高い。
- V4エンジンのフィーリング、安定した走り、所有感を満たす質感を評価する声多数。
- 「不人気」という評価は、実際のオーナーの声とは乖離がある可能性。
インターネット上で「VFR800F 不人気」というキーワードが囁かれる一方で、実際にVFR800Fを所有しているオーナーたちの声に耳を傾けると、全く異なる景色が見えてきます。各種レビューサイトやブログ、SNSなどにあふれるオーナーの声の多くは、VFR800Fに対する高い満足度を示すものです。「買ってよかった」「最高の相棒」「手放せない魅力がある」といったポジティブな評価が、ネガティブな評価をはるかに上回っている印象を受けます。では、オーナーたちは具体的にVFR800Fのどのような点に満足しているのでしょうか?最も多く聞かれるのが、やはりV型4気筒エンジンが生み出す独特の走行フィールです。低回転域でのトルク感と扱いやすさ、中回転域からのスムーズな吹け上がり、そしてVTECが作動した後の高回転域でのパワフルな加速感。この「一台で二度美味しい」とも言えるエンジン特性は、多くのオーナーにとって最大の魅力となっています。特に、VTEC作動時のサウンドの変化やパワーの盛り上がりを「官能的」「病みつきになる」と表現する声は後を絶ちません。また、V4エンジン特有の振動の少なさや、滑らかな回転フィールも、長距離ツーリングでの快適性に貢献していると評価されています。次に多く挙げられるのが、その卓越した安定性とハンドリングです。VFR800Fは、決して軽量なバイクではありませんが、走り出してしまえばその重さを感じさせない、非常に安定感のあるハンドリングを持っています。高速道路での直進安定性は抜群で、長距離を移動する際の疲労軽減に大きく貢献します。それでいて、ワインディングロードに持ち込んでも、素直なハンドリングで軽快にコーナーをクリアしていくことができます。このスポーツ性と安定性のバランスの良さが、VFR800Fをオールラウンドなスポーツツアラーたらしめているのです。
さらに、所有感を満たす上質な作り込みやデザインも、満足度を高める要因となっています。カウルの精度、塗装の美しさ、各部パーツの質感など、細部に至るまでホンダらしい丁寧な仕事が施されており、「見ていて飽きない」「所有する喜びがある」と感じるオーナーが多いようです。標準装備されているグリップヒーターやETC、トラクションコントロールといった快適・安全装備も、日常的な使い勝手やツーリングでの利便性を高め、満足度に繋がっています。もちろん、一部には「もう少し軽ければ」「VTECの作動フィールが…」「足つき性が…」といった不満点や改善要望の声も存在します。しかし、それらを差し引いても、総合的な満足度は非常に高いレベルにあるというのが、多くのオーナーに共通する評価のようです。こうした実際のオーナーの声を聞くと、「VFR800F 不人気」という説は、一部の意見や表面的な情報だけが切り取られたものであり、必ずしも実態を反映していないのではないか、と考えさせられます。むしろ、一度その魅力に触れると深く愛される、玄人好みの名車と言えるのかもしれません。
VFR800Fは乗りにくい?走行性能と快適性の実態
- VFR800F 乗り にくいと言われる理由① 車両重量と取り回し
- VFR800F 乗り にくいと言われる理由② ライディングポジションと足つき性
- VFR800F 乗り にくいと言われる理由③ HYPER VTECの挙動
- 実際の走行性能 高速道路での安定性とワインディングでの走り
- スポーツツアラーとしての快適性 乗り心地と装備
- 低速走行やUターンは苦手?街乗りでの扱いやすさ検証
- オーナーが語る「乗りにくさ」の克服法と慣れの重要性
VFR800F 乗り にくいと言われる理由① 車両重量と取り回し
- 車両重量は約240kg台と、現代のバイクとしては決して軽くはない。
- 押し引きなどの取り回しでは、その重さを実感する場面がある。
- 走り出してしまえば重さを感じさせない安定感があるとの評価も多い。
VFR800Fが「乗りにくい」と言われる理由の一つとして、まず挙げられるのがその車両重量です。VFR800F(RC79型)の装備重量は、$242kg$~$243kg$(年式による)となっており、800ccクラスのバイクとしては、決して軽い部類ではありません。例えば、同クラスのネイキッドモデルや、より軽量設計のスーパースポーツモデルと比較すると、その差は明らかです。この「重さ」が、特にバイクに乗り慣れていないライダーや、小柄なライダーにとっては、取り回しの際の負担となり、「乗りにくい」と感じさせる大きな要因になります。具体的には、駐車場での押し引きや、傾斜地での取り回し、Uターン時などに、その重さをズッシリと感じる場面があるでしょう。一度バランスを崩しかけると、支えるのが大変で、立ちゴケのリスクも高まります。特に、足つきに不安がある場合は、停車時や極低速走行時の安定感に欠け、精神的なプレッシャーを感じるかもしれません。こうした取り回し時の重さが、VFR800Fに対する「乗りにくい」「初心者向けではない」というイメージを形成している側面は否定できません。しかし、重要なのは、この重さが走行中にどのように影響するか、という点です。多くのオーナーレビューで共通して語られているのは、「走り出してしまえば、不思議と重さを感じさせない」ということです。むしろ、この適度な重さが、走行中のどっしりとした安定感に繋がり、特に高速道路での巡航時には、横風などにも強く、ライダーに安心感を与えてくれます。低重心なV4エンジンレイアウトや、よく練られたシャーシ設計により、実際の重量以上に軽快なハンドリングを実現しているとも言われています。
ワインディングロードにおいても、ヒラヒラと軽快に切り返すタイプではありませんが、ライダーの入力に対して素直に反応し、安定した旋回性能を発揮します。つまり、取り回し時の「静的な重さ」と、走行中の「動的な重さ(あるいは軽快感)」は、必ずしもイコールではないということです。もちろん、それでも絶対的な重量があることは事実であり、例えばタイトな峠道での切り返しや、ジムカーナのような俊敏性が求められる場面では、その重さがハンデとなる可能性はあります。しかし、VFR800Fが主戦場とするツーリングや、ある程度のペースでのスポーツ走行においては、この重さがむしろメリットとして働く場面も多いのです。したがって、VFR800Fの「重さ」=「乗りにくさ」と短絡的に結びつけるのではなく、どのようなシチュエーションでその重さが影響するのか、そして走行中のフィーリングはどうなのか、という点を総合的に判断する必要があります。もし購入を検討していて重さが気になるのであれば、実際に跨ってみて足つきを確認したり、可能であれば試乗して、取り回しや走行中のフィーリングを体感してみることを強くお勧めします。最初は重く感じるかもしれませんが、慣れてくれば、その安定感の虜になるライダーも少なくないはずです。
VFR800F 乗り にくいと言われる理由② ライディングポジションと足つき性
- ライディングポジションは、やや前傾姿勢のスポーツツアラー。
- ハンドル位置は調整可能だが、スーパースポーツほどではないものの前傾は感じる。
- シート高は標準的だが、車幅があるため足つき性は良好とは言えない。
VFR800Fが「乗りにくい」と感じられるもう一つの理由として、ライディングポジションと足つき性が挙げられます。VFR800Fはスポーツツアラーというカテゴリーに属し、そのライディングポジションは、スーパースポーツモデルほど極端ではないものの、やや前傾姿勢となるように設定されています。ハンドルはセパレートタイプですが、トップブリッジ上にマウントされており、スーパースポーツのように極端に低くはありません。しかし、アップライトなポジションのネイキッドバイクやアドベンチャーバイクと比較すると、明らかに上半身は前傾します。この適度な前傾姿勢は、高速走行時の風圧を軽減したり、ワインディングでのスポーティな走りを楽しんだりする上ではメリットとなります。しかし、長時間のライディング、特に市街地走行などでは、手首や肩、首への負担を感じやすく、「疲れる」「乗りにくい」と感じるライダーもいるでしょう。特に、前傾姿勢に慣れていないライダーにとっては、最初のうちは違和感や疲労を感じやすいかもしれません。VFR800F(RC79型)では、ハンドルの高さを調整できるスペーサー(ライザー)が用意されており、ある程度ポジションの自由度がありますが、それでも基本的な前傾気味のキャラクターは変わりません。次に足つき性ですが、シート高は $789mm$ と $809mm$ の2段階に調整可能で、数値だけ見れば大型バイクとしては標準的な範囲です。しかし、V型4気筒エンジンを搭載しているため、エンジン幅やフレーム幅がそれなりにあり、シート前方の絞り込みも十分とは言えません。そのため、スペック上のシート高の数値以上に、足つきが悪く感じられることがあります。特に、身長が低いライダーや、足が短いライダーにとっては、両足を地面にべったりと着けるのは難しく、つま先立ちになるケースが多いようです。
停車時や信号待ちで、片足でしっかりと車体を支えられれば問題ありませんが、前述の車両重量も相まって、足つきに不安があると、立ちゴケのリスクや精神的なプレッシャーを感じやすくなります。これが「乗りにくい」という印象に繋がることは十分に考えられます。実際に跨ってみて、自分の体格に合ったポジションか、足つきに不安がないかを確認することは非常に重要です。ローダウンキットなどを利用して足つきを改善する方法もありますが、サスペンションの性能やハンドリングに影響が出る可能性もあるため、導入は慎重に検討する必要があります。総じて、VFR800Fのライディングポジションと足つき性は、万人向けとは言えない部分があります。スポーツツアラーとしての性格上、ある程度の前傾姿勢と、それに伴う足つき性の妥協は必要になるかもしれません。しかし、そのポジションが自分の体格やライディングスタイルに合えば、長距離でも疲れにくく、スポーティな走りも楽しめる、絶妙なバランスを提供してくれます。試乗などを通じて、自分にとって「乗りにくい」のか、それとも「快適」なのかを確かめることが、購入後のミスマッチを防ぐ鍵となります。
VFR800F 乗り にくいと言われる理由③ HYPER VTECの挙動
- 約6,500rpm付近で作動バルブ数が切り替わり、パワー特性と音質が変化する。
- この切り替わり時の挙動変化を「唐突」「ギクシャクする」と感じるライダーもいる。
- 特にコーナーリング中などに作動すると、挙動を乱す要因になり得る。
VFR800Fの代名詞とも言えるHYPER VTEC機構。これは低回転域での扱いやすさと高回転域でのパワー感を両立させるための画期的なシステムですが、その独特な作動フィールが「乗りにくい」と感じられる最大の要因となっている可能性があります。HYPER VTECは、エンジン回転数が約 $6,500rpm$(RC79型の場合)に達すると、それまで1気筒あたり2つしか作動していなかった吸排気バルブが4つすべて作動するように切り替わります。この切り替わりによって、エンジンはより多くの混合気を吸い込み、排気ガスを効率よく排出できるようになり、パワーとトルクが一段と盛り上がります。同時に、排気音も「フォーン」というV4特有のサウンドから、「クォーン」という、より高周波でレーシーなサウンドへと変化します。この変化自体は、多くのライダーにとって刺激的で楽しいものと捉えられています。「VTECゾーンに入った!」という高揚感は、VFR800Fならではの醍醐味と言えるでしょう。しかし、問題となるのは、この切り替わりが「どのように」起こるか、という点です。特に初期のVTECシステムでは、この切り替わりが比較的唐突で、パワーの出方が急に変化するため、ライダーによってはギクシャクとした印象を受けることがありました。VFR800F(RC79型)では、このVTECの作動はかなりスムーズになるように改良されていますが、それでもバルブ作動数が切り替わることによるトルク変動やエンジンブレーキの効き方の変化は存在します。この変化の度合いを「スムーズ」と感じるか、「違和感がある」「乗りにくい」と感じるかは、ライダーの感覚や経験によって大きく異なります。特に問題となりやすいのが、ワインディングロードなどでコーナーリング中にVTECの作動回転数を跨いでしまうような場面です。アクセルを開けて加速している最中にVTECが作動すると、予期せぬパワーの盛り上がりによってリアタイヤのトラクションが変化したり、逆にアクセルを戻した際にエンジンブレーキの効き方が変わったりして、バイクの挙動が不安定になる可能性があります。
これが、一部のライダーから「コーナーリング中に気を使う」「VTECが邪魔」といった声が上がる理由です。経験豊富なライダーであれば、VTECの特性を理解し、作動回転数を意識しながらスムーズに走らせることができますが、初心者やVTECに慣れていないライダーにとっては、この挙動変化が「乗りにくさ」に直結する可能性があります。対策としては、VTECの作動回転数を意識し、コーナー進入前には作動回転数以下に落とすか、あるいは作動回転数以上に保ったまま旋回するなど、走り方を工夫することが考えられます。また、常にVTECが作動する高回転域を維持して走る、あるいは逆にVTECが作動しない低中回転域を中心に走る、といった乗り方で、切り替わりの影響を避けることも可能です。HYPER VTECは、VFR800Fの個性を際立たせる魅力的な機構であると同時に、その乗りこなしにはある程度の慣れやスキル、そしてライダーとの相性が求められる、やや玄人向けのシステムであるとも言えます。この機構を「面白い」と感じるか、「乗りにくい」と感じるかが、VFR800Fの評価を大きく左右する、まさに核心部分なのです。
実際の走行性能 高速道路での安定性とワインディングでの走り
- 高速道路では、車重とカウルにより抜群の安定性と快適性を発揮。
- ワインディングでは、見た目以上に軽快で素直なハンドリング。
- V4エンジンのトルクとVTECによるパワーで、スポーティな走りも楽しめる。
「乗りにくい」という評価がある一方で、VFR800Fの実際の走行性能、特に高速道路での安定性とワインディングでの走りは、多くのオーナーから高く評価されています。まず、高速道路での走行性能について見てみましょう。VFR800Fは、スポーツツアラーとして設計されており、高速巡航は得意中の得意です。前述した約 $240kg$ という車両重量は、ここでは大きなメリットとして働きます。どっしりとした安定感があり、路面の凹凸や横風の影響を受けにくく、ライダーは安心して長距離を走り続けることができます。大型のフロントカウルとスクリーンは、走行風を効果的に防ぎ、ライダーへの風圧を大幅に軽減してくれます。これにより、高速巡航時の疲労が少なく、快適なツーリングを楽しむことが可能です。V4エンジンは振動が少なくスムーズなため、長時間のライディングでも不快感が少ないのも特徴です。$100km/h$ 巡航時のエンジン回転数は、6速で $4,000rpm$ 強と比較的低めに抑えられており、エンジンにはまだ十分な余裕があります。追い越し加速なども、VTECゾーン(約 $6,500rpm$ 以上)を使えば、力強い加速を見せてくれます。クルーズコントロールは装備されていませんが、安定した速度維持は容易であり、まさに「高速ツアラー」としての資質を存分に発揮するステージと言えるでしょう。次に、ワインディングロードでの走りです。重い車体と安定志向のセッティングから、峠道は苦手なのでは?と思われがちですが、実際に走らせてみると、そのイメージは良い意味で裏切られます。低重心なV4エンジンと、剛性の高いアルミフレーム、そしてよく動く前後サスペンションにより、見た目以上に軽快で素直なハンドリングを実現しています。
コーナーへの進入では、ライダーの意思に忠実にバンクしていき、旋回中も非常に安定しています。立ち上がりでは、V4エンジンならではのトルクを活かして力強く加速していきます。特に、VTECが作動する回転域をキープして走れば、かなりスポーティな走りを楽しむことができます。もちろん、軽量なスーパースポーツモデルのような鋭い切り返しや、限界的なコーナリングスピードを求めるのは酷ですが、一般的なツーリングペースから、少しハイペースなスポーツライディングまで、幅広い領域でライダーの期待に応えてくれる懐の深さを持っています。トラクションコントロールシステム(TCS)も装備されているため、滑りやすい路面などでも安心してアクセルを開けていくことができます。ただし、前述の通り、VTECの作動フィールや、コーナーリング中に作動した場合の挙動変化には、慣れや注意が必要です。総じて、VFR800Fは、高速道路での快適なクルージング性能と、ワインディングでの楽しめるスポーツ性能を高次元でバランスさせた、非常に完成度の高いスポーツツアラーと言えます。「乗りにくい」という評価は、特定の側面(取り回しやVTECの挙動など)を捉えたものであり、走行性能全体で見れば、多くのライダーにとって満足のいく、むしろ「乗りやすい」と感じられるレベルにあると言えるのではないでしょうか。
スポーツツアラーとしての快適性 乗り心地と装備
- シートは厚みがあり、長距離でも疲れにくいと評判。タンデムも快適。
- サスペンションの動きが良く、路面からの衝撃を効果的に吸収。
- グリップヒーター、ETC、調整式スクリーンなど、ツーリングに役立つ装備が充実。
VFR800Fは、その名の通り「スポーツツアラー」であり、スポーティな走行性能だけでなく、ツーリング時の快適性も重視して設計されています。「乗りにくい」という評価とは裏腹に、快適性に関するオーナーの満足度は非常に高いものがあります。まず、乗り心地に大きく関わるシートですが、VFR800Fのシートは十分な厚みと適度な硬さがあり、長時間のライディングでもお尻が痛くなりにくいと評判です。座面も広くフラットな形状で、ライディング中の自由度も高く、快適なポジションを見つけやすいでしょう。タンデムシート(後部座席)も、比較的広く、グラブバーも装備されているため、パッセンジャー(同乗者)にとっても快適性が高いと評価されています。二人乗りでのツーリングにも適した設計と言えます。次にサスペンションですが、フロントにはインナーチューブ径 $43mm$ のテレスコピック式、リアにはプロリンク式サスペンション(プロアーム)を採用しています。これらのサスペンションは、路面の凹凸からの衝撃を効果的に吸収し、乗り心地の向上に貢献しています。特にリアサスペンションは、プリロード調整がダイヤル式で簡単に行えるため、荷物の積載量やタンデム乗車の有無に合わせて、最適なセッティングに調整しやすいのもポイントです。硬すぎず、柔らかすぎず、しなやかに路面を捉える足回りは、長距離走行での疲労軽減に繋がります。さらに、VFR800F(RC79型)には、ツーリングを快適にするための装備が標準で充実している点も見逃せません。寒い時期に重宝するグリップヒーター(5段階調整式)は、冬場のライディングの快適性を格段に向上させます。高速道路の料金所をスムーズに通過できるETC車載器(ETC 2.0対応モデルもあり)も標準装備。ウインドスクリーンは、工具を使わずに高さを調整できる機構こそありませんが、社外品などでよりハイトの高いスクリーンに交換することも可能です。
また、純正オプションとして用意されているパニアケースやトップボックスを装着すれば、積載能力を大幅に向上させることができ、長期のツーリングにも対応可能です。これらの装備は、VFR800Fが単なるスポーツバイクではなく、本格的なツーリングも視野に入れて開発されたモデルであることを示しています。ライディングポジションについては前述の通りやや前傾ですが、これも高速走行時の快適性を考慮した結果とも言えます。エンジンからの熱については、V4エンジンということもあり、特に夏場の渋滞時などでは、それなりに熱気を感じるという声もあります。しかし、これも大型バイク全般に言えることであり、VFR800Fが特別に熱いというわけではないようです。総合的に見て、VFR800Fはスポーツツアラーとして求められる快適性を高いレベルで満たしており、「乗りにくい」どころか、むしろ「快適で乗りやすい」と感じるライダーが多いのも頷けます。スポーティな走りも楽しみたいけれど、ツーリングでの快適性も妥協したくない、というライダーにとって、非常にバランスの取れた選択肢と言えるでしょう。
低速走行やUターンは苦手?街乗りでの扱いやすさ検証
- 低速域でのトルクは十分あり、発進やストップ&ゴーはスムーズ。
- 車重とやや切れ角の少ないハンドルにより、Uターンや極低速での取り回しは苦手。
- クラッチは油圧式で操作感は良好だが、重さを感じる人も。
スポーツツアラーであるVFR800Fは、高速道路やワインディングでの走行性能が高く評価されていますが、一方で日常的な街乗りでの扱いやすさ、特に低速走行やUターンが苦手なのではないか、という声も聞かれます。「乗りにくい」という評価は、こうした街中でのネガティブな印象から来ている可能性もあります。実際のところはどうなのでしょうか?まず、発進やストップ&ゴーといった、街乗りで頻繁に遭遇する場面での扱いやすさについてです。VFR800FのV4エンジンは、低回転域からでも比較的しっかりとしたトルクを発生します。そのため、アイドリング付近の回転数でも粘りがあり、発進時に神経質になる必要はあまりありません。HYPER VTECが作動しない低回転域(約 $6,500rpm$ 以下)では、2バルブ作動となるため、レスポンスも穏やかで、ギクシャクしにくい特性を持っています。クラッチ操作に関しては、油圧式クラッチを採用しており、操作感はスムーズで節度があります。ただし、レバーの重さについては、「軽い」と感じる人もいれば、「長時間操作していると疲れる」「もう少し軽くても良い」と感じる人もおり、個人差があるようです。渋滞路など、クラッチ操作が頻繁になる状況では、この重さが負担になる可能性はあります。次に、懸念されることが多いUターンや極低速での取り回しについてです。これに関しては、やはり「得意ではない」と言わざるを得ません。約 $240kg$ という車両重量と、スポーツバイクとしては標準的ですが、ネイキッドバイクなどと比較するとやや切れ角が少ないハンドルが、その主な理由です。Uターンをする際には、車体を傾けながらハンドルを切る必要がありますが、重い車体を低速でコントロールするのは、ある程度の慣れとスキルが必要です。足つきに不安がある場合は、さらに難易度が上がります。
幅の狭い路地での方向転換や、駐車場での細かい切り返しなども、やはり気を使う場面が多くなるでしょう。エンスト(エンジンストール)については、低速トルクがあるため比較的しにくいエンジンですが、油断していると、極低速でのクラッチ操作ミスなどでエンストさせてしまう可能性はあります。重い車体でエンストすると、バランスを崩して立ちゴケに繋がりやすいので注意が必要です。街乗りでの扱いやすさという点では、軽量なバイクやスクーターと比較すると、やはり不利な面があることは否めません。しかし、これも「慣れ」の問題が大きい部分です。VFR800Fの特性を理解し、丁寧な操作を心がければ、街乗りで極端に苦労するということはないでしょう。ただし、バイク通勤などで毎日、混雑した市街地を走るような使い方をメインに考えている場合は、VFR800Fの持つ魅力(ツーリング性能やスポーツ性能)を十分に活かせず、むしろ扱いにくさを感じる場面が多くなるかもしれません。VFR800Fは、やはりその本領を発揮するのはツーリングやワインディングであり、街乗りは「こなせる」けれど「得意ではない」というのが正直なところかもしれません。
オーナーが語る「乗りにくさ」の克服法と慣れの重要性
- 「乗りにくさ」は、バイクの特性を理解し、慣れることで克服できる部分が大きい。
- 取り回しは、重心の位置を意識したり、傾斜を利用したりする工夫で楽になる。
- VTECの挙動は、作動タイミングを意識した走り方を身につけることでコントロール可能に。
VFR800Fに対して「乗りにくい」という評価があることは事実ですが、多くの現役オーナーたちは、その「乗りにくさ」とされる部分を、バイクの特性として理解し、慣れや工夫によって克服しています。むしろ、その「じゃじゃ馬」的な部分を乗りこなすことに喜びを見出しているライダーも少なくありません。「乗りにくさ」を克服するためのポイントは、やはり「慣れ」と「理解」に尽きると言えるでしょう。まず、取り回しの重さについてです。これは物理的な重量なので軽くすることはできませんが、扱い方にはコツがあります。例えば、押し引きする際には、バイクの重心がどこにあるかを意識し、できるだけ車体を垂直に保つように心がけること。そして、力を入れる方向を進行方向にまっすぐ向けることなどが挙げられます。わずかな傾斜でも利用すれば、少ない力で動かすことができます。また、サイドスタンドを出す位置や、バイクを停める向きを工夫するだけでも、日々の取り回しの負担は軽減されます。最初は重くて大変に感じるかもしれませんが、毎日触れているうちに、自然と効率的な力の入れ方やバランスの取り方が身についてくるものです。次に、ライディングポジションや足つき性です。ポジションの微調整(ハンドルスペーサーの利用など)や、シートのアンコ抜き(クッション材を減らす加工)、ローダウンキットの導入などで、ある程度は改善が可能です。しかし、根本的には、そのポジションで長時間快適に走るための筋力や体力をつけること、そして足つきに不安があっても、片足でしっかりと車体を支える技術を身につけることが重要になります。これも、乗り続けることで自然と体が適応していく部分が大きいでしょう。そして、最もVFR800Fらしい「乗りにくさ」の要因であるHYPER VTECの挙動です。
これに関しては、まずVTECがどの回転数で作動し、その際にどのような変化(パワー、トルク、音、エンジンブレーキ)が起こるのかを、身体で覚えることが第一歩です。慣れてくれば、VTECの作動タイミングを予測し、意図的に作動させたり、逆に作動させないように回転数をコントロールしたりすることが可能になります。例えば、コーナーリング中にVTECゾーンに入りそうな場合は、進入前にもう一段シフトダウンして回転数を上げておく、あるいはアクセル操作をより繊細に行う、といった工夫が考えられます。最初は戸惑うかもしれませんが、VTECの特性を理解し、それを活かした走り方ができるようになると、VFR800Fを操る楽しさは格段に増します。多くのオーナーが語るように、VFR800Fの「乗りにくさ」とされる点は、決して乗り手を選ぶような致命的な欠点ではなく、むしろバイクとの対話を楽しみながら乗りこなしていく、奥深い魅力の一部と捉えることもできるのです。もちろん、どうしても自分の体力やスキル、ライディングスタイルに合わない、と感じる可能性もあります。だからこそ、購入前の試乗は非常に重要です。しかし、もしVFR800Fの持つ他の魅力(V4エンジン、デザイン、ツアラー性能など)に強く惹かれるのであれば、多少の「乗りにくさ」は、時間をかけて付き合っていく中で、きっと乗り越えられるはずです。
まとめ:VFR800Fの評価 「不人気」「乗りにくい」は本当か?
- 「不人気」というよりは、独自の個性を持つ「ニッチな人気」モデル。
- V4エンジンやVTECは、魅力であると同時に好みが分かれる要因。
- ライバルと比較してスペックや価格面で不利な点もあったが、独自の価値を持つ。
- デザインは洗練されているが、特徴的なフロントマスクは賛否両論。
- 生産終了により希少価値は増し、中古市場では安定した人気を維持。
- 「乗りにくい」要因として、車重、ポジション、VTEC挙動が挙げられる。
- 車重は取り回しで感じるが、走行安定性に貢献。走り出せば軽快。
- ポジションはやや前傾、足つきは良好とは言えず、体格を選ぶ面も。
- VTECの挙動は慣れが必要だが、乗りこなせばVFRならではの楽しみに。
- 走行性能、快適性は高く、スポーツツアラーとして非常にバランスの取れたバイク。
- 「乗りにくさ」は、慣れと理解、工夫で克服できる部分が大きい。
最後までこの記事を読んでいただき、本当にありがとうございます!バイク大好き運営者です。
「VFR800F 不人気」「VFR800F 乗りにくい」…そんなキーワードを目にして、ちょっと不安になったり、あるいは「そんなはずない!」って思ったりして、ここに辿り着いてくれたのかもしれませんね。
正直に言うと、VFR800Fは、誰にでも手放しでおすすめできるタイプのバイクではないかもしれません。V4エンジン、HYPER VTEC、独特のデザイン、そして決して軽くはない車体…。確かに、他のバイクと比べると、少しクセがあるというか、乗り手を選ぶ部分を持っているのは事実です。まるで、ちょっと気難しいけど、付き合ってみるとすごく魅力的な友人みたいですよね。
でも、この記事を読んでいただいて、その「クセ」が、実はVFR800Fのたまらない魅力の一部でもある、ということが少しでも伝わったら嬉しいです。低回転では扱いやすく、回せばVTECが炸裂して豹変するエンジン。重いはずなのに、走り出すと安定感と軽快さが同居する不思議な感覚。そして、眺めているだけでも満足できる、ホンダならではの上質な作り込み。
「不人気」なんて言われることもありますが、それはきっと、このバイクが持つ深い魅力を知らない人の声。本当にVFR800Fを愛しているオーナーさんたちの満足度は、めちゃくちゃ高いんです。私も、初めてVTECゾーンに入れた時の、あの音と加速の変化には鳥肌が立ちました。「これか!」って。
もしあなたが今、VFR800Fに興味を持っているなら、ぜひ一度、実車に触れて、できれば試乗してみてください。スペックやネットの評判だけでは分からない、あなた自身の感覚で、このバイクとの相性を確かめてほしいんです。もしかしたら、最初は少し「乗りにくい」と感じるかもしれません。でも、ちょっと時間をかけて付き合ってみれば、きっと他には代えがたい、最高の相棒になってくれる可能性を秘めたバイクだと思います。
あなたのバイク選びが、最高にハッピーなものになることを心から願っています! VFR800Fという素晴らしいバイクとの出会いが、あなたのバイクライフをより豊かにしてくれますように。